雑記
2008/9/25
なわばりばり
beko

【縄張】
築城に際しての基本設計を縄張(なわばり)あるいは径始(けいし/経始とも表記される)といい、その中心は曲輪の配置にあった。“縄張”の語源も曲輪の配置を実地で縄を張って検証したことに由来するとされる。-wikipedia
最近お城関係のお仕事が多いせいか、普段の趣味+αでお城の形状について調べてます。
現在の天守閣のある、所謂一般に「城」と呼ばれるものは、室町時代末期から、江戸時代初期に建てられたものがほとんどです。
その立地条件も時代がすすむにつれて、防御中心の山城から、政務に優れた交通の要所に建てられた平城へと進化しています。
また、鉄砲、大砲の登場がそれまでの攻防城戦において重要な位置を占めるにつれ、城も対重火器戦に特化したものへと進化しています。
そして、江戸時代が来ると一国一城令により、また、明治維新の際には廃城令、第二次世界大戦を経て、そのほとんどが姿を消したのでした。
建築物でありながら美術的にも非常に優れているお城、個人的にはぜひ現存12天守巡りなんてチャレンジしてみたいですね。
築城に際しての基本設計を縄張(なわばり)あるいは径始(けいし/経始とも表記される)といい、その中心は曲輪の配置にあった。“縄張”の語源も曲輪の配置を実地で縄を張って検証したことに由来するとされる。-wikipedia
最近お城関係のお仕事が多いせいか、普段の趣味+αでお城の形状について調べてます。
現在の天守閣のある、所謂一般に「城」と呼ばれるものは、室町時代末期から、江戸時代初期に建てられたものがほとんどです。
その立地条件も時代がすすむにつれて、防御中心の山城から、政務に優れた交通の要所に建てられた平城へと進化しています。
また、鉄砲、大砲の登場がそれまでの攻防城戦において重要な位置を占めるにつれ、城も対重火器戦に特化したものへと進化しています。
そして、江戸時代が来ると一国一城令により、また、明治維新の際には廃城令、第二次世界大戦を経て、そのほとんどが姿を消したのでした。
建築物でありながら美術的にも非常に優れているお城、個人的にはぜひ現存12天守巡りなんてチャレンジしてみたいですね。
今なら最強の城が縄張れそうな予感が…。
カサギ
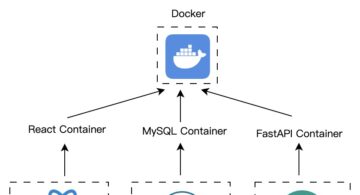 2025/01/10
2025/01/10 2024/03/01
2024/03/01 2023/12/01
2023/12/01 2023/06/23
2023/06/23 2023/02/24
2023/02/24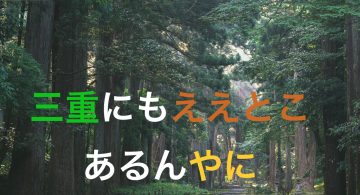 2022/12/16
2022/12/16 2022/06/24
2022/06/24 2022/06/17
2022/06/17